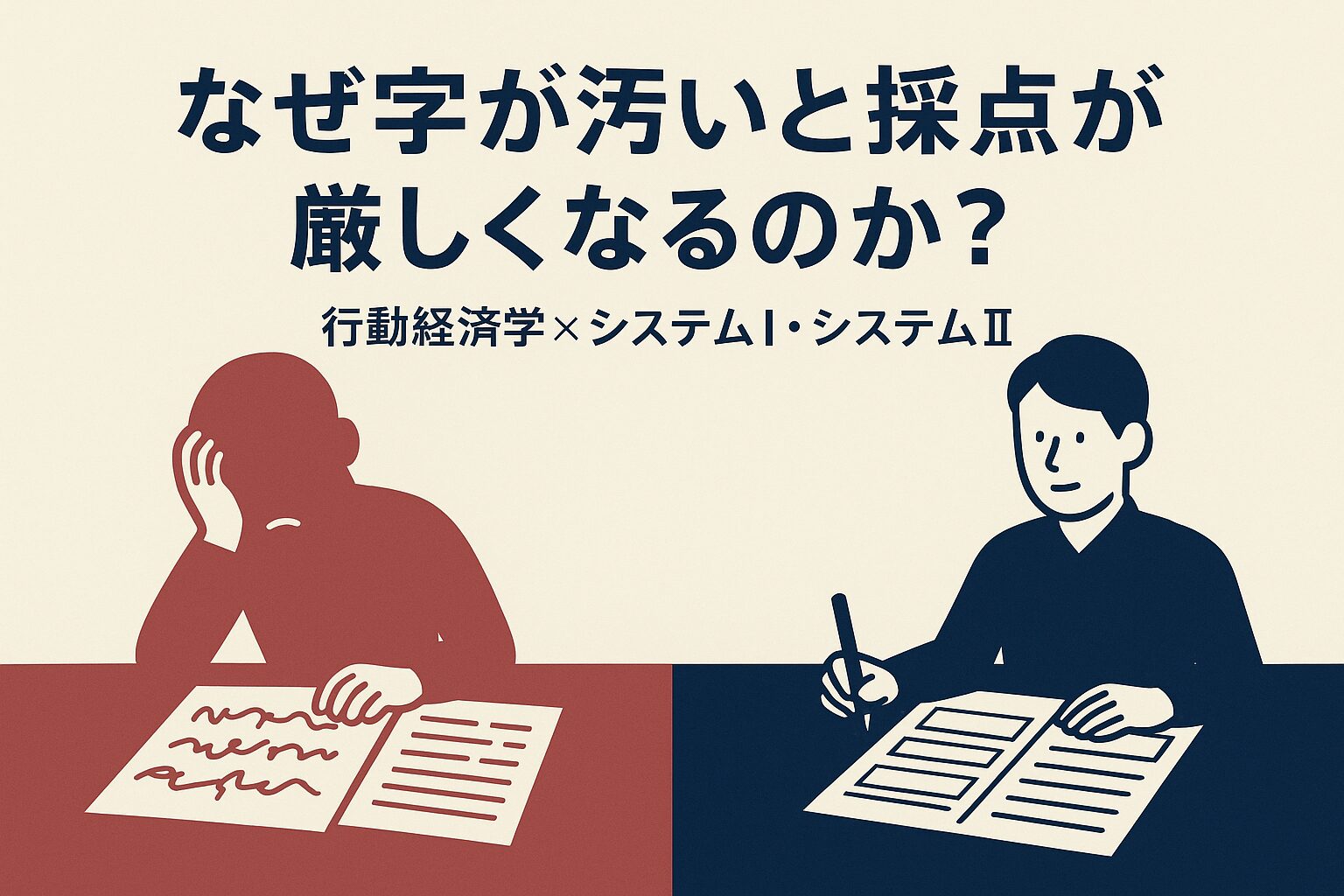目次
字が汚いだけで損をしていないか?
「内容は合っているはずなのに、点数が伸びない」
「模試で“字をもう少し丁寧に”とコメントされた」
こうした経験、心当たりはありませんか?
一部では、
字が汚いと、採点者の気分が悪くなって、厳しく採点される
という話もよく聞きます。
もちろん、採点者はできる限り公平であろうとします。
それでもなお、「読みやすさ」や「見やすさ」が評価に影響してしまうことは、行動経済学の観点からも十分に説明できます。
鍵になるのが、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンが提示した
「システムⅠ」と「システムⅡ」という2つの思考モードです。
この記事では、
-
なぜ字が汚いと厳しく採点されやすいのか
-
行動経済学で重要なシステムⅠ・Ⅱの観点から、その裏側で何が起きているのか
-
その知識を、試験対策だけでなくビジネス・マーケティングにどう活かせるか
までを整理していきます。
最後にもう一度タイトルの問い
「なぜ字が汚いと厳しく採点されるのか?」
を回収しつつ、実践的な対策もまとめます。
なお、この記事で扱っているシステムⅠ・システムⅡの考え方は、
行動経済学の名著『ファスト&スロー』で詳しく解説されています。
記事の最後で、本書についても簡単にご紹介します。
第1章 システムⅠ・システムⅡとは何か(行動経済学の基本)
まずは、行動経済学でよく登場する2つの思考モードをシンプルに押さえておきましょう。
1-1. システムⅠ:速く、自動で、直感的に
システムⅠは、自動的・無意識的・直感的な思考システムです。
-
2+2=? → すぐ「4」と出てくる
-
友人の顔を見て、誰かを瞬時に認識する
-
「危ない!」と思わず体が避ける
こうした瞬間的な判断や反応は、ほとんどがシステムⅠによるものです。
特徴をまとめると:
-
処理が速い
-
努力をほとんど感じない
-
感情や印象に強く影響される
-
過去の経験則(直感・勘)に基づきやすい
-
そのぶん認知バイアス(思考の偏り)が生じやすい
行動経済学では、このシステムⅠが生むバイアス(アンカリング、ハロー効果など)が、人間の「非合理な判断」を引き起こすと説明されます。
1-2. システムⅡ:遅く、意識的で、論理的に
システムⅡは、意識的・論理的・努力を要する思考システムです。
-
17×24を暗算する
-
複雑な文章を読み、内容を理解する
-
新しい戦略の企画を考える
のように、エネルギーを使って考える場面で働きます。
特徴は:
-
処理は遅い
-
集中と努力が必要
-
ルールや論理に基づいて判断する
-
計算・比較・シミュレーションが得意
-
ただしすぐ疲れてサボる(システムⅠに任せたがる)
行動経済学では、「人は常に合理的に考えている」のではなく、この“疲れやすい”システムⅡを節約しようとする結果、システムⅠに頼りすぎて非合理な行動をとる、と考えます。
1-3. 「2つの脳」ではなく「2つのモード」
よく誤解されますが、システムⅠとⅡは「脳の別の部位」というわけではありません。
あくまで情報処理のモードの違いを説明するための概念です。
-
同じ人の中に、両方が常に存在する
-
状況によって、どちらが主導権を握るかが変わる
-
行動経済学は、「どの場面でどのモードが働きやすいか」を明らかにしてきた学問
と捉えると、実務にも落としやすくなります。
試験の採点も、ビジネスの評価も、マーケティングも、
この2つのモードがどう動いているかを理解すると、見え方がガラッと変わります。
第2章 なぜ字が汚いと厳しく採点されるのか?(システムⅠ・Ⅱで分解)
ここから、タイトルの問いに本格的に踏み込みます。
2-1. 読みにくい答案は、採点者の「システムⅡ」に負荷をかける
採点者は、1日に大量の答案を読み続けます。
その中で、
-
一文字一文字を目を凝らして読まないといけない
-
行間が詰まりすぎていて見づらい
-
どこに何が書いてあるかパッと分からない
といった答案に出会うと、読むだけでエネルギーを消耗します。
ここでフル稼働しているのが、
「意識的に、努力して読む」システムⅡです。
システムⅡは、集中力や意志力を大きく消費するため、すぐに疲れてしまうのが特徴です。
疲れた状態では、人は無意識のうちに、
-
細かく見るのが面倒になる
-
ミスを見落としたり、逆に厳しめに判断したりする
-
「この答案はちゃんとしてなさそう」という印象を持ちやすい
といった状態になりがちです。
行動経済学の観点から見ると、これは「認知負荷が高い情報は、評価が厳しくなりやすい」という典型的なパターンです。
2-2. 第一印象をつくる「システムⅠ」がマイナスに傾く
答案をパッと見たとき、最初に働いているのはシステムⅠ(速い思考)です。
-
きれいに整った字
-
適度な行間
-
段落分けや番号振りで構造が分かる
こうした答案は、第一印象で「ちゃんとしていそう」「読みやすそう」というプラスの感情を生みます。
逆に、
-
字がつぶれている
-
大きさや傾きがバラバラ
-
余白がなく、紙が真っ黒に見える
といった答案は、一瞬で「読みにくそう」「雑そう」という印象を与えます。
この第一印象の違いが、その後の採点に微妙なバイアスをかけます。
行動経済学・社会心理学で知られるように、ある一部の印象が全体の評価に影響することを「ハロー効果」と呼びます。
字が雑そう → 内容も雑そう
読みにくい → 間違いも多そう
という連想が、無意識レベルで働きやすくなるわけです(システムⅠの自動的な反応)。
2-3. 採点プロセスで起きていることを分解する
答案1枚が採点される流れを、システムⅠ・Ⅱで分解してみましょう。
-
一瞬見たときの「印象」:システムⅠ
-
「読みやすそう」「なんか大変そう」がここで決まる
-
-
実際に読み進めて理解する:システムⅡ
-
字が汚いと、ここで大きな認知負荷がかかる
-
-
微妙な部分をどう解釈するか:システムⅠ+システムⅡ
-
好印象なら「ここは意図が伝わっている」と好意的に解釈
-
悪印象なら「ここはちゃんと書けていない」と厳しめに解釈
-
このとき、字が汚い答案は、
-
ステップ1でマイナス印象(システムⅠ)
-
ステップ2で読解コストが高く、システムⅡが疲れる
-
ステップ3で「厳しめの解釈」に傾きやすい
という二重の不利を受けていると考えられます。
2-4. 内容が同じでも評価がブレるメカニズム
もちろん、採点基準がしっかりしている試験では、「字が汚いからバツにする」ということは基本的にありません。
ただし、
-
判定が微妙な表現
-
一部がかすれていて読み間違えのリスクがある
-
部分点をどれくらいつけるか判断が分かれる
といったグレーゾーンでは、採点者の「印象」が無意識に影響する余地がどうしても生まれます。
-
読みやすく論理も追いやすい答案 → 「ここは意図が伝わっている」と好意的に解釈
-
読みにくく構成もバラバラな答案 → 「ここはちゃんと書けていない」と厳しめに解釈
こうして、内容がほぼ同じでも、最終的な点数に差がつくケースが起こり得ます。
これは採点者が「意地悪をしている」のではなく、
システムⅠ・Ⅱという人間の思考の特性が生み出す、ある種の“仕様”だと考えた方が近いでしょう。
行動経済学の役割は、こうした「見えないバイアス」を言語化してくれるところにあります。
2-5. 読みやすい字・構成がもたらす「地味だけど大きな差」
逆に、読みやすさに気を配るだけでも、次のようなメリットがあります。
-
システムⅠが「好印象」を持ちやすい
-
システムⅡの負荷が下がり、内容に集中してもらえる
-
微妙な表現も「好意的に」読んでもらえる可能性が上がる
具体的には、
-
1行の文字数を詰め込みすぎない
-
行間に余白を取る
-
設問ごとに段落・番号を振る
-
図や表を使うときは見やすい位置に配置
など、「見た目の設計」だけでもかなり変えられます。
第3章 この知識は試験だけで終わらせない:ビジネス・マーケへの応用
ここからがマーケター・ビジネスパーソン向けの本題です。
実は、「字が汚いと損をする」という話は、そのままビジネスの現場にも当てはまります。
行動経済学の視点を持っておくと、あらゆる「評価される場面」の設計が変わります。
3-1. 上司やクライアントも「採点者」と同じ状態
-
上司に提出する企画書
-
クライアントに出す提案書
-
社内で共有するレポート
これらをチェックする人も、1日に何本も資料を見ています。
-
文字が小さすぎる
-
情報が詰め込みすぎで、どこを見ればいいか分からない
-
図表がごちゃごちゃしている
こうした資料は、採点者が「読みにくい答案」を見たときと同じく、システムⅡに大きな負荷をかけます。
結果として、
-
本来のアイデアの良さが伝わらない
-
「なんとなくピンとこない」と却下される
-
ライバルの“読みやすい資料”に負ける
といったことが、普通に起きてしまいます。
3-2. マーケティングクリエイティブも同じ構造
-
LP(ランディングページ)
-
サービスサイト
-
セールスレター
-
広告バナー
も、実は「採点される答案」と同じです。
ユーザーは、
-
ファーストビューを一瞬見て印象を持つ(システムⅠ)
-
興味があればスクロールして内容を読み込む(システムⅡ)
というプロセスを踏みます。
ここで、
-
ファーストビューがごちゃごちゃしていて何のページか分からない
-
文字ばかりで読みにくく、段落も整理されていない
といった状態だと、**内容がどれだけ良くても「読まれない」「信じてもらえない」**ことになります。
行動経済学を踏まえると、
-
システムⅠ向けに「一瞬で分かる・良さそうと感じる」デザイン・コピー
-
システムⅡ向けに「ちゃんと納得できる」情報設計・根拠・比較
の両方を用意することが重要になります。
第4章 「字で損をしない」ためのチェックリスト
最後に、タイトルの問い
「なぜ字が汚いと厳しく採点されるのか?」
をもう一度まとめて回収しつつ、今日からできる対策を整理します。
4-1. メカニズムのまとめ
字が汚いと厳しく採点されてしまうのは、
-
第一印象(システムⅠ)が「雑そう」「読みにくそう」に傾き、
-
読み取りにコストがかかり、システムⅡが疲れ、
-
グレーな部分の解釈が厳しめに振れやすくなる
という2つの思考モードの性質が重なっているからでした。
これは試験だけでなく、ビジネス資料やマーケティングでも同じように起きています。
行動経済学は、こうした「評価のブレ」がどこから生まれるかを説明してくれるレンズだと言えます。
4-2. 試験・仕事・マーケ共通のチェックリスト
答案・資料・LPなどを見直すときに使えるチェックリストです。
-
1画面(1ページ)で伝えたいメッセージは1つに絞れているか
-
行間・余白は十分にあり、「真っ黒」に見えないか
-
見出しや番号で構造がすぐに分かるか
-
重要なキーワードが埋もれていないか
-
初めて見る人でも、ストレスなく読めるかを想像しているか
-
「システムⅠの第一印象」と「システムⅡの認知負荷」を意識して設計しているか
第5章 内容を活かすのは「中身」だけでなく「見せ方」
-
字が汚いと厳しく採点されやすいのは、採点者のシステムⅠ・Ⅱの性質によるもの
-
第一印象と認知負荷が、無意識に評価を歪めてしまう
-
これは試験に限らず、ビジネス資料やマーケティングにもそのまま当てはまる
だからこそ、
「内容さえ良ければ、字や見た目は関係ない」
とは考えず、
「内容を最大限に活かすために、読みやすさも設計する」
という発想が重要になります。
行動経済学が教えてくれるのは、
人はいつも合理的ではなく、システムⅠとシステムⅡのバランスの中で判断しているということです。
この視点を持っておくと、
-
勉強のしかた
-
資料のつくり方
-
LP・広告の設計
すべてで「同じ原理」が見えてきます。
行動経済学を体系的に学びたい方へ
この記事では、行動経済学のキーワードであるシステムⅠ・システムⅡに絞ってお話ししましたが、
実際には、私たちの判断や行動に影響するバイアスはもっとたくさんあります。
-
なぜ人は「得するより損したくない」と感じるのか
-
なぜ最初に見た価格に引きずられてしまうのか(アンカリング)
-
なぜ「みんなが選んでいる」と聞くと安心するのか(社会的証明)
こうした人間の“非合理さ”を体系的に学ぶなら、行動経済学の名著を押さえておくのがおすすめです。
『ファスト&スロー(上・下)』ダニエル・カーネマン
システムⅠ・システムⅡという概念を提示した、行動経済学を代表する1冊です。
-
システムⅠ(速い思考)とシステムⅡ(遅い思考)の仕組み
-
私たちが日常的に陥っている認知バイアス
-
なぜ人は合理的に判断できないのか、その背景
が、豊富な実験例とともに解説されています。
この記事で触れた
-
「第一印象に引っ張られるハロー効果」
-
「認知負荷が評価を歪める」
といったテーマも、より深く理解できるようになります。
行動経済学が最強の学問である [ 相良 奈美香 ]
一方で、「もっとサクッと・日本語で行動経済学の全体像を掴みたい」という方には、この一冊がおすすめです。
-
行動経済学がビジネスや日常生活でどう役立つのか
-
有名な実験や行動バイアスが、かみ砕いた言葉で解説されている
-
数式ほぼゼロで読みやすく、「とりあえず1冊目」にちょうどいい
といった特徴があり、
-
『ファスト&スロー』=じっくり基礎を固める“本格派テキスト”
-
『行動経済学は最強の学問である』=まず全体像を掴む“わかりやすいガイド”
という関係で使い分けると、とても学びやすくなります。